 をクリックすると小ウィンドウが開き、音楽が流れます。
をクリックすると小ウィンドウが開き、音楽が流れます。 をクリックすると小ウィンドウが開き、音楽が流れます。
をクリックすると小ウィンドウが開き、音楽が流れます。韃靼人の踊り ロシア国民楽派の作曲家ボロディンによる歌劇「イーゴリ公」第2幕の音楽。 韃靼人(正しくはポロヴェツ人)が捕虜となったイーゴリ公に踊りを披露する場面で用いられた。 バレエ・リュスではミハイル・フォーキンの振り付けにより 一幕物のバレエとして独立させ、 1909年パリ・シャトレ座にて初演した。 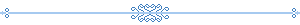 シェエラザード リムスキー・コルサコフ作曲の交響組曲。 「海とシンドバッドの船」「カランダール王子の物語」「若き王子と王女」 「バグダッドの祭、海、青銅の騎士のある岩にての難破、終曲」の4楽章からなる。 バレエの内容はこの表題とは関係ない。 バレエの内容はこちらで。 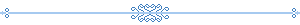 ボレロ 初期のバレエ・リュスに参加していたダンサー、イーダ・ルビンシュテーインが、 自らの主演作として作曲をラヴェルに、振り付けをニジンスカ(ニジンスキーの妹)に依頼し 1928年に初演されたのがオリジナル版である。 舞台はアンダルシアの居酒屋で、ロマの女がテーブルの上に乗って踊りだし、 やがて忘我の境地に入って踊り続ける女の周りで、 男たちも踊るという内容であった。 「ボレロ」は男女どちらでも踊れる両性具有的な曲であり、 ベジャールを初めとするその後の振付家もその要素を踏襲している。 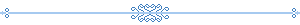 作品64-2(ショパン) 「レ・シルフィード」で使用された曲の一つ プリマ・バレリーナと男性ソリストによるパ・ド・ドゥの場面で用いられる。 「レ・シルフィード」ではショパンのピアノ曲を管弦楽曲に編曲して演奏され、 ロシアでは「ショピニアーナ」と呼ばれる。 「レ・シルフィード」についてはこちらで。 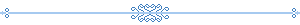 牧神の午後への前奏曲 ステファヌ・マラルメの詩をもとにドビュッシーが作曲。 ニジンスキーがバレエ化して1912年に初演された。 作品についてはこちらで。 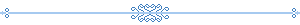 |